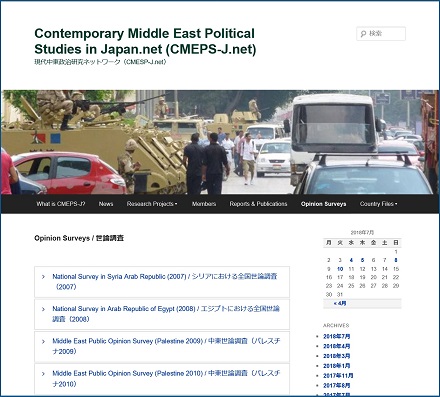研究室紹介Seminar
□ゼミナール
□卒業論文
□修士論文
□博士論文
ゼミナール
 近年の西アジア・北アフリカ(中東)地域情勢、とりわけアラブ地域情勢は、同地域から発信される情報が政治的偏向を免れず、また欧米(さらには日本)のメディアやアカデミアがこうした情報の是非を充分検証しないままに無批判に受け入れる傾向が強いため、実情把握が困難になっています。とくに西アジア・北アフリカ(中東)地域で起きている政治的な出来事のなかには、現実とはまったく異なった評価・解釈がなされているものさえあります。
近年の西アジア・北アフリカ(中東)地域情勢、とりわけアラブ地域情勢は、同地域から発信される情報が政治的偏向を免れず、また欧米(さらには日本)のメディアやアカデミアがこうした情報の是非を充分検証しないままに無批判に受け入れる傾向が強いため、実情把握が困難になっています。とくに西アジア・北アフリカ(中東)地域で起きている政治的な出来事のなかには、現実とはまったく異なった評価・解釈がなされているものさえあります。こうした現状を踏まえて、本ゼミナールでは、今日のアラブ地域を中心とする西アジア・北アフリカ(中東)地域で起きている政治的な出来事を、可能な限り現実に即したかたちで把握することを目指します。具体的には、西アジア・北アフリカ(中東)地域における近年の政治変動を扱った日本語および現地語の一般書・研究書の輪読、個人研究などを通じて、「民主化」、「権威主義」、「体制転換」、「紛争」、「人権」、「主権」、「内政干渉」、「宗派主義」、「民族主義」、「イスラーム主義」、「テロとの戦い」などについて批判的に考察します。
卒業論文

2024年度
■「第1次・第2次スィースィー政権における雇用政策:国内の失業問題への影響に注目して」■「イランの中のアゼリー人:2000 万人の「マイノリティ」」
■「トルコ外交の戦略的反抗:スウェーデンのNATO加盟問題を巡って」
■「第二次ナゴルノ・カラバフ紛争からトルコが得たもの:カフカスの地域紛争が持つ重要性」
■「イラクに顕現する深く厚い壁:マーリキー首相の政策から、イラク第2回国民議会選挙の敗因を紐解く」
■「ヨルダンでのシリア難民の児童結婚はなぜ無くならないのか」
■「湾岸小国の外交に見る敏捷性:カタルによる対リビア軍事介入をよみとく」
■「存続するフール・キャンプ:PYDのビジョンとアラブ系部族との対立」
■「スィースィー政権下における祖国未来党の位置づけ:三度の選挙を通じた段階的変遷」
■「開発の起点としてのスエズ運河:2015年前後のスエズ運河を見て」
■「カタールのソフトパワー政策におけるオーディエンス:メディア政策と開発援助政策からの検討」
■「現代イランにおける女性教育」
2023年度
■「ヨルダン・コンパクトをめぐる思惑:見過ごされた実情」■「レバノン政治の脆弱性とシリア難民政策への影響:経済危機下での政策の分析(2019~2022年)」
■「予期せぬ連帯が可能となるとき:現代イランの抗議活動と統治をめぐる「享楽の政治」」
■「シリアにおける社会主義経済導入の要因とその変容」
■「経済推移から見る公正発展党期トルコにおける外交政策の変遷」
2022年度
■「イスラム国が暴力行為から得ている効用:心理学的、解剖学的アプローチ」■「ドファール戦争におけるアラブ系住民の離反」
■「「レンティア」としての難民:パレスチナ難民、シリア難民がヨルダンにもたらした利益」
■「イラクの隙間で⽣活するイスラーム国」
■「ペルシア・アイデンティティとイスラーム・アイデンティティ:ドバイ万博イラン・パビリオンの分析を通じて」
2021年度
■「モロッコのクスクス:食材面における特徴」■「「民間人保護」はなぜ守られないのか:シリア内戦へのロシアの介入を例に」
■「ジハード団の動員構造:フレーミング概念からの分析」
■「クウェートはなぜ民主化の足を止めたのか」
■「トルコにおけるシリア難民の社会統合の現状」
■「経済から紐解くパレスチナの日本語教育事情:すれ違いの30年」
■「イラクの体制転換:不安定な国の苦しみ」
■「エジプトの障害女性:複合差別の構造から読み解く周縁化の歴史」
■「イラン対外戦略に関する一考察:アンサール・アッラーへの支援を事例として」
■「なぜトルコでフェミサイドがなくならないのか」
■「なぜトルコ共和国においてイスラムは政治の道具になり得るのか:ギュレン運動を例に」
2020年度
■「干ばつはいかにして脅威になったのか:自然環境と社会制度からみるダルフールの紛争」■「カイロの都市化と景観の変化」
■「エジプトにおける反政府デモとソーシャルメディアの役割についての考察:2011年と2019年のデモを比較して」
■「揺れ動くアイデンティティ:アッシリア人キリスト教徒の闘争」
■「一時婚がイランに与える政治的メリットとは」
■「国際的に活躍するイラン人映画監督の作品の変化」
■「トルコ・イスラエル関係はなぜ悪化したか:トルコの外交政策とイスラーム世界におけるユダヤ教徒の歴史から紐解く」
■「イラクと安定:アメリカ占領統治とイラク戦争後の復興」
■「財政危機の端緒:レバノンにおける財政赤字の累積」
■「現代イランにおける伝統医学」
■「シリアにおけるアラブ民族主義とクルド民族主義:理論と実践の乖離」
■「現代パレスチナ人女性の恋愛プロセス:宗教と政治の観点から」
2019年度
■「ムスタファ・ケマルのイスラーム政策とその後のトルコ共和国」■「サーレハとイエメンの22年:アリー・アブドゥッラー・サーレハの政治手法」
■「イスラーム国の外国人戦闘員の処遇:9.11事件をもたらしたアラブ・アフガン現象からの教訓」
■「日本によるパレスチナ国家承認」
■「ヨルダン王制の生存戦略:統治構造と外交政策からの考察」
■「新西アジア・北アフリカ駱駝商戦:キャメルミルク下剋上宣言」
■「門戸開放政策の中の社会主義:エジプト経済政策の試み」
■「アラブ地域におけるエジプトのプレゼンスはなぜ低下したか」
■「イスラーム法からみるイラン生体間プログラムの正当性」
■「乙女ファッション戦争:イスタンブルvsアンカラ」
2018年度
■「イスラームのスィースィー:2010年代エジプトにおける宗教と政治」■「政党政治が切り拓く多様な国民の政治参加と国家発展への道のり:ヨルダン人のヨルダン人によるヨルダン人のための政治を実現するために」
■「Crimes of Honor in Jordan」
■「1970年代の門戸開放政策はエジプトの社会経済にどのような変容をもたらしたのか」
■「ユダヤ性とシオニズムの乖離」
■「BDS運動から考える対イスラエル・ボイコットの可能性」
2017年度
■「The Suez Crisis:スエズ運河の国有化はナセル政権にどのような功罪をもたらしたのか」■「共存のための政策:ドイツにおけるシリア難民」
■「大衆抗議運動を模索するパレスチナの青年達:社会内部に見る阻害要因の検討」
■「タハッルシュ:エジプトのセクシャル・ハラスメントの実態」
■「シリアの規制緩和政策」
■「エジプト経済政策の検討:ムバーラク政権とムルスィー政権の比較」
■「権力掌握のための憲法宣言:2011~2013年のエジプト」
2016年度
■「肉の宗派主義:レバノン食文化における宗派主義考察」■「分離壁がイスラエルのユダヤ性に及ぼす影響:ユダヤ国家存続の模索」
■「ヨルダン王制が存続している理由:政治体制とエスニシティ統治からの考察」
■「革命後のチュニジアにおけるイスラーム主義」
■「アラブ諸国におけるパレスチナ難民政策の差異:ヨルダンおよびレバノンを事例として」
■「現代エジプトにおけるムスリム同胞団:支持獲得への模索」
■「シリア紛争の主要な当時者による国内避難民政策の功罪:シリア政府、クルド民族主義勢力、反体制組織」
■「ホロコーストがイスラエルにもたらすもの:ユダヤ人歴史学者ラブキンの主張をめぐって」
2015年度
■「ヨルダンにおける水利権確保による政治不安定化の抑止」■「イラク・クルディスタン地域政府におけるイスラーム国台頭の影響」
■「現代パレスチナ・イスラエルにおけるサマリア人:「紛争地域」で再興を果たした少数集団の歩み」
■「イラク・ナショナリズムの模索」
■「「イスラーム国」は何故、世界の脅威となったのか:軍事的側面からの考察」
2014年度
■「アラブ・イスラエル紛争における外国人の社会運動:オスロ合意以降を中心に」■「政権を担うエジプト軍:軍部介入を歓迎する国民の心はいかに」
■「レバノンの「テロ組織」ヒズブッラーは如何にして政党として成功したか?」
■「シリア紛争と学生の社会運動:民衆の国民若いへの願いはいかにして政策に採用されうるか」
■「イスラエルにおけるユダヤ教の役割:シオニストの求める「ユダヤ教」とは」
2013年度
■「ハーフェズ・アサドとバッシャール:シリア大統領に求められた資質」■「占領政策をめぐるイスラエルの司法判断:入植と分離壁を中心に」
■「エジプト2011年の民衆蜂起における「アハラーム」紙の言説分析:編集長はなぜ謝罪したのか?」
■「なぜエジプトのムルスィー大統領はパレスチナ問題政策を転換できなかったのか」
■「「緑の運動」の変遷と分析:なぜ「緑の運動」は成功しなかったのか」
■「リビアのムアンマル・アル=カッザーフィー大佐の西側諸国に対する姿勢:「義務を果たす」の発言をめぐって」
 2012年度
2012年度
■「パレスチナの政治体制:ヤースィル・アラファートとマフムード・アッバースの為政者としての性格」■「パレスチナ・イスラエルにおける分離壁からみる抵抗運動」
■「バハレーン、民主化の波打ち際:2011年バハレーン争乱の考察」
■「南スーダン分離独立の意義:独立前の状況からの検討」
2011年度
■「社会運動としての2011シリア・アラブの春:運動の発生要員と性格の分析、および評価」■「ヨルダン国民にとっての王制:体制存続が持つ意味」
■「オスロ体制にみる和平プロセスの崩壊:過激派の暴力が及ぼす影響」
■「リーダーなき革命はなぜ生まれたのか:エジプト1月25日革命における社会運動体の役割」
■「イスラエルのパレスチナ人の政治運動:グリーンラインの内側で「パレスチナ国家建設」が持つ意味」
■「パレスチナの労働運動:誕生からインティファーダへの軌跡」
2010年度
■「パレスチナの女性による抵抗運動:その変遷と現代に生きる女性たち」■「レバノン政治家ジュンブラートの転向」
2009年度
■「アスマー・アル=アフラス・シリア大統領夫人のシンボルと政治的役割」■「僕がイスラーム抵抗運動に参加する可能性について」
■「二民族一国家の真実:イスラエル・パレスチナ問題解決への糸口となるのか」
■「パレスチナの否定された抵抗運動:アル=アクサー・インティファーダ(2000~2006年)の検討」
■「現代レバノンにおけるテレビ放送と政治勢力:メディア・システム論を中心に」